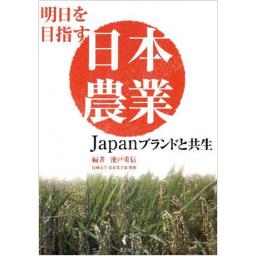1) ジェフリー・サックス : 貧困の終焉, 早川書房 (2006)
2) 新名惇彦 : 植物力, 新潮社 (2006)
3) FAO : FAO世界農業予測 : 2015-2030年 前編 : 世界の農業と食料確保, 国際食糧農業協会 (FAO協会) (2003)
4) バーツラフ・スミル : 世を養う, 農文協 (2003)
5) 速水佑次郎, 神門善久 : 農業経済論, 新版, 岩波書店 (2002)
6) ビョルン・ロンボルグ : 環境危機をあおってはいけない, 文藝春秋 (2003)
7) ミッチェル, インコ, ダンカン : 世界食料の展望, 農林統計協会 (1999)
8) レスター・ブラウン : フード・セキュリティー, ワールドウォッチジャパン (2005)
9) 時子山ひろみ, 荏開津典生 : フードシステムの経済学, 第3版, 医歯薬出版 (2005)